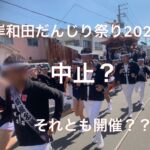おはようございます。
花寄せの時期だけ連絡してくるヤツが嫌いな管理人AKIRAです。
さて、暑い夏のシーズンが終わると泉州人にとってワクワクする祭りの季節ですね。
9月は岸和田だんじり祭りだけですが、10月はいろんな地区でだんじりが曳行しています。
岸和田市のお隣、貝塚市もだんじり祭りが盛んに行われ、毎年多くのギャラリーが訪れます。
そんな中で、今日は貝塚市木島地区にある三ツ松町のだんじりを紹介したいと思います!
貝塚のだんじりは3地区
貝塚のだんじりは3地区に分かれて曳行しています。
南海本線「貝塚駅」周辺は麻生郷地区と呼ばれており、半田、堀、久保、石才、麻生中 、東、海塚、小瀬の8台のだんじりが曳行。
南近義神社周辺の南近義地区では、窪田、地蔵堂、堤 、王子、橋本の6台。
水間鉄道「名越駅」周辺から「水間観音駅」南側一帯の木島・西葛地区には木積、名越、三ツ松、水間、馬場、清児、森の7台があります。
三ツ松町だんじりの特徴
三ツ松町のだんじりは平成17年に新調されただんじりで、屋根は切妻型のだんじりでタッパが3800cmの少し大きいのが特徴です。
大下工務店で制作され、彫師が木下彫刻工芸さんの木下賢治さんと言う方が担当されたようですね。
新調当時は、横の方の町旗も紺色に仕上げられているのがあまり見た事が無かったので凄く新鮮だった記憶があります!
個人的には先代の真ん中が緑と横が赤の町旗が好みですが、間近で見させて頂いくとやはり紺色の町旗も負けじと味があります。
宮入りの場所は?
宮さん(宮入する神社)が貝塚市の森にある森稲荷神社と言うひっそりとした所にある神社に宮入りします。

森稲荷神社は、古くから木島谷の総社と呼ばれ、もとは東方の山頂にありました。
泉州をはじめ各方面から多くの参詣者を集め、江戸後期に中盛彬が著した地誌「架利素米農比登理囲棋止(かりそめのひとりごと)」には、天正年間(1573~1592)の繁栄が記されています。
その他、あの岸和田藩主だった岡部氏も田畑を寄進しているんです。
そんな由緒ある森稲荷神社には、名越・清児・水間・三ツ松・森の5台のだんじりが宮入りします。
日程: 10月9日(日)
場所: 稲荷神社 AM10:00~
名越・清児・水間・三ツ松・森
やり回しの時、笛を吹かない!?
さて、話は戻りますが三ツ松町はタイトルでも書いたように笛がない町なんです。
笛が無いってどゆこっちゃねん!って思われた方もいらっしゃると思いますが
三ツ松町のだんじりは、やり回しの発進の時に笛を吹かないんです。
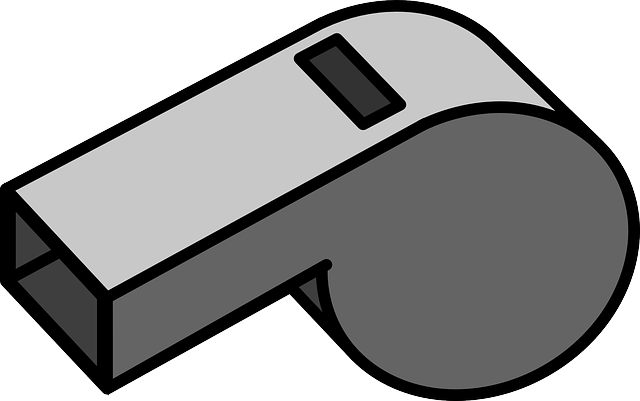
だんじりを愛してやまなく曳いてる男の子なら1度は憧れた団長の笛ってのが無いようですね(汗)
じゃあどうやって発進するのか?
だんじりファンな方ならお気付きの方もいるかと思うのですが、団長の「笛」じゃなくて団長の「声」で発進するんです。
まず、いつでも走れる準備が出来たら副団長がうちわを上げ
「よっしゃ行くぞ!張れ!!」
と、この時に曳き手は綱を、団長は声を張らしてアドレナリンを一気に増幅させるんです。
徒競走で言うクラウチングスタートのよーい!と言われてお尻を上げた時の瞬間ですね(笑)
そして、「よっしゃ!」の声と共に足を掻ぎ鳴物がやり回しのリズムに変わり走る!と言うスタイルですねー。
曳き手の方たちも、「わー!!」と声を掛け合ってまさに町の一体感が見れるのが見所です!
笛がない事でみんなで声を上げ合って士気や一体感を作る事で今まで三ツ松町のやり回しは、「早い!イカツい!ドリフトや!」と今までにたくさん聞いて来ましたが
ここに言われて来た秘密があるんでは無いでしょうか?
しかし、まだここで終わりではありません。
もう1つここで三ツ松スタイルを紹介したいと思います。
それは…せーの!!鳴物ですね(笑)
停止線で止まった時に鳴物が変わりますよね?
三ツ松町は、どうやら鉦(かね)発進の鳴物らしいですがところがどっこい
団長が号令を太鼓の方に向けてるではありませんか!!!
そして笛の方も太鼓に合図を送っているではありませんか!!
そうなんです、やり回しの時鳴物の発進が太鼓発進に変わるんです。
あれれー?鉦発進じゃ無かったのぉ?
と、僕がコ〇ンくんなら言ってしまうかも知れません(笑)
最後に…三ツ松町のやり回しは数年前に最後に見たっきりですが、掛け声といい、早さと言い、ドリフトのやり回しと言い
やはりもう1度見たい!!三ツ松のだんじりに会いたくて会いたくて震えると思わせてくれるやり回しでした。
皆さんも1度、貝塚三ツ松のだんじりを見に行ってはいかがでしょうか^_^